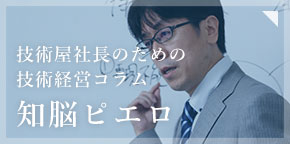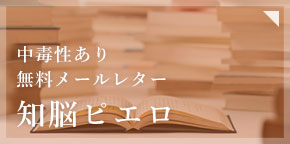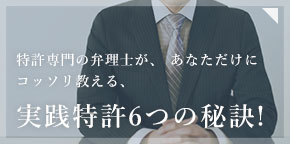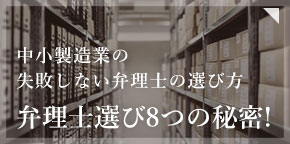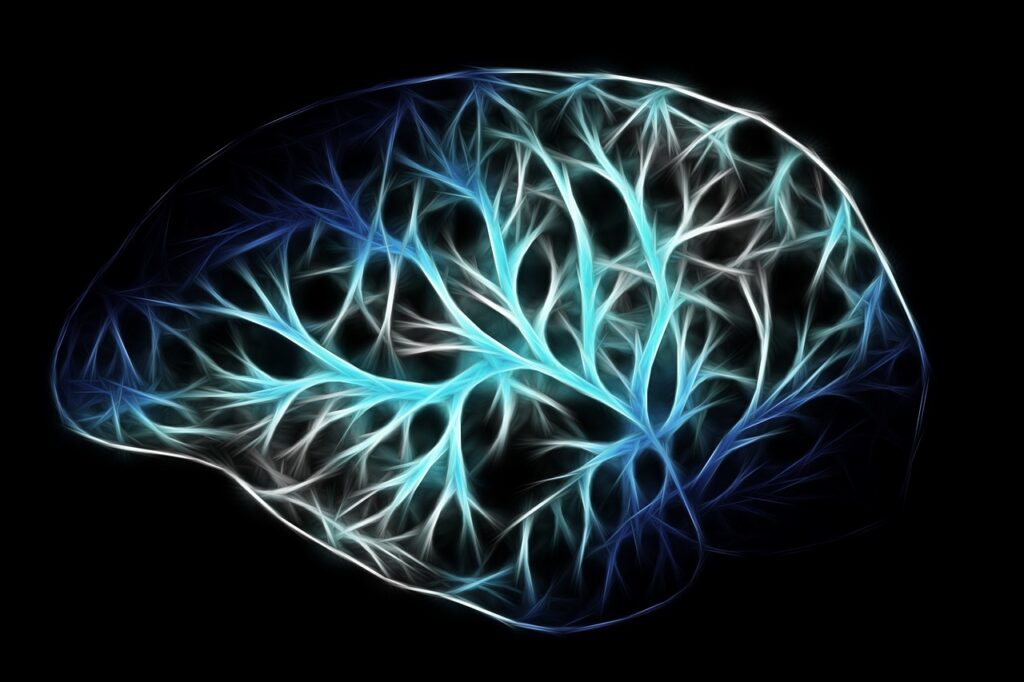
今回は、知財のお話しです(^^)
最近、生成AIが熱いですね(^○^)
生成AIの急速な浸透を受けて、
知財法の改正が議論されてます(`ε´)
法改正というのは、
事実が先に起こって、
その事実に対応させるように
後追いで進められていく、
ということが一般的ですね(^_^)
法改正が検討されるということは、
生成AIの現実の影響が
大きくなってきたからです(・o・)
でも、法改正すると言っても、
そもそも生成AIが浸透する社会が
どうなるかがよく分からない状態ですので、
完璧に対応させるのは難しいでしょう(>_<)
現状の不具合を少しずつ
改正していくといった感じでしょうか。
その1つとしては、
生成AIと発明者の問題がありますね。
生成AIを使って発明を創造した場合、
誰が発明者になるのか?
という問題です(^_^)b
現状の特許法では、
発明者は、ヒトだけです(^o^)
つまり、生成AIを使っても、
発明者になれるのは、
生成AIを使って発明を創造した
そのヒトのみということですねd(^_^o)
しかし、これについては、
改正が検討されます(^_^)
つまり、生成AIを開発した人も
「共同発明者」として
発明者になれるかどうかを
検討する段階に入るそうです(・o・)
背景としては、
製薬会社による創薬開発の
影響が大きいようですね(^o^)
創薬開発というのは、
莫大な資金と時間がかかります。
それを、専用のAIを使って
開発すれば、安く早くすることができますね。
ちなみに、2024年のノーベル化学賞は、
タンパク質の立体構造を予測するAIの
開発者が受賞しました(°°)
中外製薬なども独自AIを使って
開発しているそうです(^_^)v
政府は、
このような巨額の資金が動くような
製薬業界において、
AI開発者も発明者と認めることによって、
開発促進を図ろうとしているんでしょうかね。
でも、AI開発者というのは、
チャットGPTみたいな
汎用的な生成AIの場合は
どうなるんでしょうかね?
もし、これらも発明者とするとなると、
米国に利益が吸い取られるような
負のイメージもありますよね(>o<)
その辺の線引きがどうなるかは、
難しいところですね(^_^)b
さらに、オモシロいのは、
新規性についての検討もするらしい。
生成AIと新規性って何か?
これは、既存の商品を無断で
生成AIに学習させて、
生成AIによって発明品が
大量に作られて公開される、
なんてことが起こり得るということ。
特に、製薬業界では、
化学式を大量に公開されたりすると、
新規性喪失により、
特許が取れなくなる可能性もあります。
なので、生成AIによる
新規性喪失の手当てについても
法改正がなされるそうです(^o^)
まだ、検討に入る、という段階ですので、
どうなるかは分かりませんが、
今後の展開を見まもっていきたいですね。
それでは、次回もお楽しみに!
━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●
・AIにより法改正が検討!
・AI開発者は発明者?
・AIによる新規性喪失はどうなる?
━━━━━━━━━━━━━━━
代表弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ